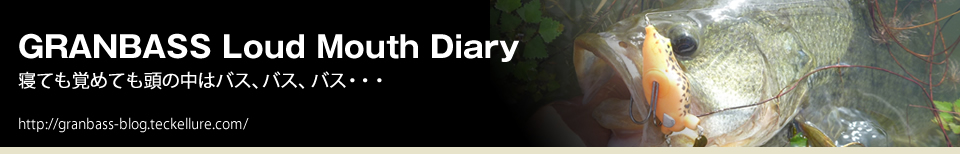スーパースプークを使わずしてペンシルを語るべからず。スーパースプークはペンシルベイトの名作です。日本にはヘドンマニアの方がたくさんいて、オリザラ(オリジナルザラスプーク)のファンは多いですが、スーパースプークを愛用している人は以外に少ないように思います。ボクは長年アメリカで釣りをしてきて、数多くの釣り人のタックルボックスを覗いてきましたが、アメリカではオリザラよりもスーパースプークの方が圧倒的に人気です。最近になって、ようやく日本でもその実力が認められ、スーパースプークを意識したルアーがラッキークラフトやジャッカルからアメリカマーケットを意識してリリースされ始めています。
スーパースプークを使わずしてペンシルを語るべからず。スーパースプークはペンシルベイトの名作です。日本にはヘドンマニアの方がたくさんいて、オリザラ(オリジナルザラスプーク)のファンは多いですが、スーパースプークを愛用している人は以外に少ないように思います。ボクは長年アメリカで釣りをしてきて、数多くの釣り人のタックルボックスを覗いてきましたが、アメリカではオリザラよりもスーパースプークの方が圧倒的に人気です。最近になって、ようやく日本でもその実力が認められ、スーパースプークを意識したルアーがラッキークラフトやジャッカルからアメリカマーケットを意識してリリースされ始めています。
話は少しそれますが、アメリカではあまりペンシルベイトといういい方が浸透していないように思えます。確かにペンシルベイトといえば通じますが、アメリカ人がペンシルベイトと言うのを聞いた覚えがほとんどありません。アメリカでは一般にスプークタイプベイトとか、ウォーカーベイト、スティックベイトと呼ばれています。
スーパースプークはシンプルな構造ですが、非常に良くできたルアーです。水平浮き気味の浮力を抑えたボディーはしっかり水にかみながら左右に大きくスライドします。その水押し効果と後部の大きなウェイトボールがカコン、カコンと奏でる大音響のラトルサウンドで、ディープのビッグバスも水面におびき出すアピール力を持っています。毎年ネバダ州レイクミードで開催されるUSオープンでは、スーパースプークは大人気です。今年のUSオープンで優勝したジャスティン・カーもスーパースプークがメインベイトだったそうですし、過去にも何度かウィニングルアーになっています。毎年、USオープン出場者の半数以上の人がスーパースプークを1度はキャストしていると思います。ボクも以前、USオープンに参戦したときは、炎天下の中、スーパースプークのみで釣りをしたこともあります。
ただ、この名作にも、ダイブしやすいという欠点があります。浮力を抑えた水平浮きのため、一度水中にヘッドが突っ込むと、そのまま水中でアクションしてしまうので、一度手を止めて、浮き上がるのを待たないといけません。しかも浮き上がりが遅く、テンポ良く使えず、ストレスとなることがあります。慣れるとずいぶんマシですが、それでも波気のあるときは、非常に扱いにくくなります。
 かつて日本で一世を風靡し、入手するのも困難なプレミアものだったステイシー90ですが、今ではすっかり陰を潜めています。確かにステイシー登場以来、多くのロングリップミノーが発売されたのも理由でしょうが、このカテゴリーのルアー自体が流行りません。猫も杓子もポンプリトリーブだった時代が懐かしいです。ステイシーの名前の由来が何かの雑誌でステイ(止めて)・シー(見せる)だったと読んだ記憶がありますが、アメリカでは恥ずかしくて言えませんね。
かつて日本で一世を風靡し、入手するのも困難なプレミアものだったステイシー90ですが、今ではすっかり陰を潜めています。確かにステイシー登場以来、多くのロングリップミノーが発売されたのも理由でしょうが、このカテゴリーのルアー自体が流行りません。猫も杓子もポンプリトリーブだった時代が懐かしいです。ステイシーの名前の由来が何かの雑誌でステイ(止めて)・シー(見せる)だったと読んだ記憶がありますが、アメリカでは恥ずかしくて言えませんね。 ボクのブログって、現行モデルよりも旧モデルの方がよかったという話が多いですが、このステイシー90に関してはバージョン2の方がボクの好みです。日本ではオリジナルのステイシーの人気が高く、売れすぎて(作りすぎて)金型が壊れて、バージョン2になったとか言われています。その割には昨年にはオリジナルが復刻されましたが、あまり話題にはなりませんでした。もう完全に過去のルアーって扱いでした。結局のところ、オリジナルの金型は壊れていなかったのか、それとも新しく金型を作り直したのか、気になるところですが・・・。
ボクのブログって、現行モデルよりも旧モデルの方がよかったという話が多いですが、このステイシー90に関してはバージョン2の方がボクの好みです。日本ではオリジナルのステイシーの人気が高く、売れすぎて(作りすぎて)金型が壊れて、バージョン2になったとか言われています。その割には昨年にはオリジナルが復刻されましたが、あまり話題にはなりませんでした。もう完全に過去のルアーって扱いでした。結局のところ、オリジナルの金型は壊れていなかったのか、それとも新しく金型を作り直したのか、気になるところですが・・・。 バージョン2はボクにとって、なくてはならない一軍ルアーで、今でも現役バリバリです。今月末に開催されるトーナメントでも当然、投入予定です。そもそもステイシーって、オリジナルはポンプリトリーブ用、バージョン2はジャーキング(リッピング)用で、使い方がまったく違いますよね。アメリカでポンプリトリーブなんて、やっている人を見たことありませんから、オリジナルはアメリカ人にはウケが悪かったんでしょう。そこでジャーキング用としてアメリカマーケット向けに生まれたのがバージョン2なのでしょう。実際アメリカではオリジナルモデルはほとんど販売されていなかった(昨年販売?)ので、アメリカではステイシーといえばバージョン2を指します。
バージョン2はボクにとって、なくてはならない一軍ルアーで、今でも現役バリバリです。今月末に開催されるトーナメントでも当然、投入予定です。そもそもステイシーって、オリジナルはポンプリトリーブ用、バージョン2はジャーキング(リッピング)用で、使い方がまったく違いますよね。アメリカでポンプリトリーブなんて、やっている人を見たことありませんから、オリジナルはアメリカ人にはウケが悪かったんでしょう。そこでジャーキング用としてアメリカマーケット向けに生まれたのがバージョン2なのでしょう。実際アメリカではオリジナルモデルはほとんど販売されていなかった(昨年販売?)ので、アメリカではステイシーといえばバージョン2を指します。